
『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。
平安時代、身につける衣に香りを焚きしめることは、
高貴な男女の身だしなみとして欠かせないものでした。
非常に高価で貴重な渡来物だった香料を用いて作られる薫香は、
香りを聞いた一瞬で
その方の身分から人格・教養までを表現してしまうため、
貴族らは熱心に創意工夫して自らの香りの調合に努めたのです。

「ボタン唐草蒔絵伏籠・阿古陀香炉」田村資料館
衣服に香りを薫きしめる道具として用いられたものに伏籠(ふせご”)とよばれるものがあります。灰を盛った香炉に火をくべて香をくゆらせ、竹や木製の枠に網をはめこんで作られた伏籠を被せ、その上に着物をひろげ立ち上ってくる芳ばしい薫煙を染み込ませるという仕掛けです。これからご紹介する香料は、
すべてが私たちの住む地球という星から誕生した天然香料です。
人間は多くの香りある植物や鉱物などの中から特にこれらを選び出し、
医術・薫香・香辛料など人が生きのびるため
また、生活を豊かにするために活用してきました。
ぜひこれらの香料ひとつひとつの姿を眺め
豊かな芳香をゆっくりと嗅いでみてください。
もしかしたら、あなたの中にうずもれていた
太古の人々の感性が呼び覚まされるかもしれません・・・。
~薫物・匂い袋に使用される11種の香料~
中国や朝鮮を経由して日本へと伝えられた様々な香料。
聖徳太子の生きた飛鳥時代、
それらは渡来したばかりの教え“仏教”の
特別な儀式のためにのみ使用されるたいへん貴重なものでした。
その後、奈良時代にはいると唐の高僧・鑑真和上によって
数種の香料を調合してつくる薫物(練り香)の処方が伝えられます。
いままでに嗅いだこともない優雅で雅なその芳香は、
平安の宮人たちの心を一瞬にしてとりこにしてしまうのでした。
当時の香料は、
その多くがインド・東南アジアなどの熱帯地域に産するもの、
ゆえにすべてがたいへん入手困難で高価なものだったのです。
僧侶や貴族などごく限られた一部の人々しか
見ることができなかった香料を、
現代に生きる私たちは誰もが手にすることができます。
しかし、自然が破壊されひとたび争いが起こってしまえば、
またたくまにこれらは過去のものとなってしまうことでしょう。
特長あるこれらの香料を手にとると、
平和であることの幸せ大切さをしみじみと感じるのでした。
それでは薫物や匂い袋などに使われる代表的な十一種の香料をご紹介しましょう。
(1) 白檀(ビャクダン)【樹幹】
私達のもっとも馴染みのある香木「白檀」はインドを代表する産物で
とくにマイソール産は“老山白檀”といわれ最高級品として扱われています。
ほとんどのお香の主原料となり幹だけでなく枝や根も使用されますが、
樹木の芯部ほど良質で官能的な芳香をはなちます。
白檀には心を落ち着かせる重さと
まとわりつくような甘さがそなわっており、
古来より神聖な香木としてあがめられ
その材で仏像や調度品なども製作されました。
しかし半寄生植物で栽培が困難なことから年々入手が難しくなり、
近年インドでは伐採・輸出規制がかかり
価格は何倍にも高騰しています。

クスノキ科常緑高木の樹皮の部分。
肉桂・ニッキともいわれ、
ピリッとした爽やかな刺激のある甘さが特徴です。
桂皮の芳香は東洋はじめヨーロッパなど世界中で愛されており
香料・健胃の生薬・香辛料としてなど多用されています。

ヒマラヤ高地や中国・インドに産する
オミナエシ科の植物を乾燥させたものです。
辛味のある強い香りは他の香料と合わせることで厚みを増し、
より複雑な芳香に仕上げることが出来るでしょう。

インドネシアのモルッカ諸島原産の丁香樹の
花の蕾を摘み取り乾燥させたもので、
現在はアフリカ東部およびマダカスカルなどで栽培されています。
コショウと並ぶ代表的な香辛料でもあり、
ヨーロッパの肉魚料理やインドのカレーのほか
菓子やアルコール類の風味付けにも用いられています。
この香辛料を求めて大航海時代がはじまったことは有名ですが、
丁子には非常に高い抗菌・防腐効果がそなわっています。

マレーシアなど南アジア原産のシソ科の多年生植物で、
パチューリともいわれ大変クセのある独特の香りを持つ植物です。
しかし不思議なことに慣れるにつれ
恋しくも感じられる芳香といえるでしょう。
十九世紀、インドのカシミヤ製ショールはヨーローッパへと輸出されました。
大切なショールを虫食いから守るため
カッ香の匂いをしみこませた箱をもちい
枝を忍ばせて船積みをしたといわれます。
なぜならばカッ香には強力な防虫効果があり
運搬中に発生する蛾の幼虫の虫食いを抑えることができたのです。
はたしてインドのオリエンタルな香りをまとったショールは、
爆発的に人気を博するのでした。

バイ貝の一種である巻貝の蓋の部分を砕いたもので、
その独特の香りは練り香の保留材として重要な役割を果たします。
古来は中国南海産のものが主でしたが、
現在は南アフリカ・モザンビークのものが中心となります。

インドネシア原産の龍脳木から採取される樹脂です。
スーとして非常に強い清涼感の香気を放つ白い鱗片状の結晶は
墨の高貴な香りに用いられたことで有名です。
龍脳はマルコ山古墳の草壁皇子の遺骨からも出土しており
千五百年前すでに日本で使用されていたことがわかります。

中国・インドシナ・マレー半島に産するシクンシ科の落葉高木で、
果実は褐色の卵型をしています。
その昔は薬用として大変に有効な幻の果実として珍重され、
その香りの高さから香料としても用いられました。
室町時代、日本ではこの実をかたどった掛香が布地で作られるようになり、
邪気をはらう魔よけの意味合いをもって飾られました。

中国南部やインドシナなどのごく限られた地域に生育する、
モクレン科の常緑樹に実る八角茴香
(別名スターアニス)といわれる星型の香料。
非常に強く野性味あふれるガンとした芳香をもちます。

中国を原産とするサクラソウ科の植物の茎や根を乾燥させたもの。
大地を思わせる野性的な芳香ながら、
スッとしたクールで清涼感あふれる心地よい香りをもちます。
粉末にして線香の原料などにも良く使われています。

キク科モッコウの根で、芳香性の薬物植物です。
日本では古来より薫香用のほか、生薬としても用いられてきました。
肩こりや高血圧のほか婦人系の病に効果があります。
良く似た“青木香(ショウモッコウ)”はウマノスズクサ科の根で、
やはり薫香や生薬につかわれるため
混同されやすいので注意が必要です。
ご紹介した香料の中には
非常に個性的でクセの強く感じられる香料も多々ありますが、
それらの香料も他の素材と合わさることによって
じつに奥行きのある香りの世界を作り出すことが出来るのです。
『源氏物語』では源氏が亡くなられた後の世を描いた十三帖のうち、
後半の十帖を特に「宇治十帖」と称して独立させた読み方がなされています。
主人公として二人の魅力的な貴公子が登場しますが、
彼らの性格は光源氏のもつ陰陽の部分を二分するかのように描かれました。
~薫君・薫大将(かおるのたいしょう)~
光源氏の年の離れた正妻“女三宮”と
若き貴公子“柏木”との間に生まれた不義の子で、
源氏はこの事実を知りつつも表向きは実子として彼に接します。
罪を背負い生まれてきた薫君は、
うすうす自らの出生の秘密を知るにつれ、
どこか厭世的で憂いを秘めた青年に成長していきました。
彼の性格は光源氏の“陰の部分”を表しているといわれますが、
彼は生まれながらにして
“なんともいえず不思議な芳香”を身体に備えていました。
その香りの素晴らしさは、文中でこのように表現されています。
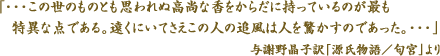
彼と同じように中国には身体に芳香を持つ美女のお話が残されています。
その代表ともいえるのが、
“香妃(こうひ)”や“楊貴妃(ようきひ)”などでしょう。
唐の玄宗皇帝(げんそうこうてい)に溺愛された楊貴妃は、
湯浴みをした水にまで良い香りがうつったといわれていますが、
当時異民族の強い体臭は珍重される傾向がありました。
イラン系の血を引く美女だったといわれる彼女には、
東洋人にはない独特なエキゾチックな体臭が具わっていたのかもしれません。
~匂宮・匂兵部卿宮(におうひょうぶきょうのみや)~
彼は光源氏の孫に当たる方で、
源氏と“明石の御方”との間に生まれた姫君が帝と結ばれてできた貴公子です。
生まれながらにして地位・名誉・美貌・才能など
あらゆる条件をもち合わせた彼は人々の注目に値する輝かしさをもって生まれ、
プレイボーイで情熱的な源氏の“陽の部分”を備えていました。
薫君と匂宮の二人は仲の良い友人関係を築きつつ立派な青年へと成長しますが、
様々な面でのライバルでもありました。
とくに不思議な芳香を具えた薫君をうらやましく思う匂宮は、
ことのほか香りに対して競争心を燃やします。
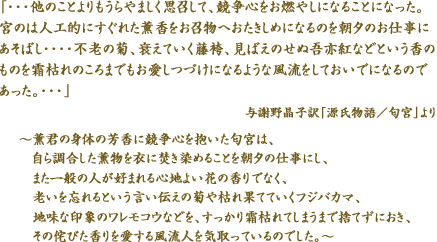
なにかにつけ好敵手の二人ですが、
薫君にはいかに優れた処方の薫物にも勝る不思議な芳香が身体にそなわっており
こと香りに関して匂いの宮は薫君に勝ることができなかったようですね。
「カヲル」とは、
香りや煙がどこからともなく漂い感じられるように
“目に移らない精神的な風情の美しさ”を表すことに用いられました。
それに対して「ニホウ」とは、
古代において“視覚的色彩の美”を表す言葉でした。
「丹(ニ)」とは魔除けの意味をもつ朱もしくは赤を
「穂(ホ)」とは突出することで、
「ニホウ」という言葉は「赤があざやかに美しく外に輝きだす」
という意味に使われていたのです。
ゆえに、「薫君」と「匂宮」と言う彼らの名前からも、
内面的美と視覚的美という二人の美しさの違いが感じ取れることでしょう。

薫君の身体から発する香りは、
恋の場面でさらに強さを増し去った後にも強烈に彼の面影を残すのでした。
薫君の恋の遍歴は、
仏門に対する憧れと女性に対する執着が交差して入り混じり、
香りのようにユラユラと揺れ動いていくことになります。
「源氏物語」では、この二人の貴公子に愛されたがゆえに
死を決意する姫君“浮船”との物語を最後に、
結論らしい幕切れの言葉もなく最終章「夢の浮橋」で終わりをむかえます。
急に幕が降ろされたように筆をおいた紫式部ですが、
ここにもまた彼女の何がしかの意図がこめられているのかもしれません。

